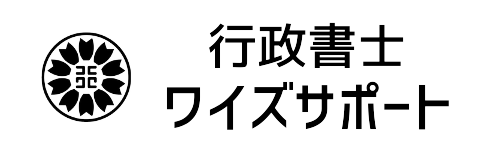「何年も親の介護をしてきたのに、相続は兄弟で平等?」
そんな不公平感を抱える方は少なくありません。
実は、介護などによって被相続人に特別な貢献をした場合、その取り分を増やす制度があるのをご存じですか?
今回は、寄与分制度を中心に、介護してきた子どもが相続で報われるためのポイントを解説します。
そもそも「寄与分」って何?

介護した分だけ、多くもらえる制度があるってこと?

はい。「寄与分」は、他の相続人より特別な貢献をした人の取り分を増やせる制度です。
「寄与分」とは、相続人の中で被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人に、その貢献度を加味して相続分を加算できる仕組みです。
代表的な例としては:
- 長期間にわたって親を介護した
- 親の事業を手伝い、財産の維持に貢献した
- 生活費や医療費を負担していた
寄与分を主張するための条件

誰でも寄与分が認められるの? どんな証拠がいるの?

相続人であること、無償での貢献があったこと、財産維持への効果があったことの3点がカギです。
寄与分が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります:
- 相続人であること(他人や相続人でない人は「特別寄与料」の対象)
- 無償で特別な貢献をしたこと
- 財産の維持または増加に寄与していること
つまり、ただ同居していただけ、少し世話をしていたという程度では足りず、経済的に見て明確な貢献が必要です。
介護の実態をどう証明する?

介護記録や医療費の支払い、近所の人の証言など、日頃の積み重ねが証拠になります。
寄与分を認めてもらうには、証拠の裏付けが重要です。以下のようなものが有効です:
- 介護日誌やメモ
- 病院・介護施設との連絡記録
- 介護のために使った費用の明細
- 地域包括支援センターの記録
- 近所の人や親戚の証言
それでももめたときはどうする?

兄弟が納得してくれない場合は、どうすればいいの?

家庭裁判所に調停を申し立てることができます。専門家の助けを借りましょう。
寄与分を巡って相続人同士で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停や審判になります。
第三者である裁判官や調停委員を通して話し合うことで、冷静な解決を図ることができます。
まとめ
- 長年の介護が報われる「寄与分」制度がある
- 無償で特別な貢献をしたことが条件
- 日々の記録と証拠の積み重ねが重要
- 争いになったら家庭裁判所の調停も視野に
「親の面倒を見た分は報われたい」──そう感じたら、まずは事実を整理し、専門家のアドバイスを受けましょう。
寄与分の主張には法的な知識と実務の経験が欠かせません。お困りの際は、私たち専門家へ相談を。