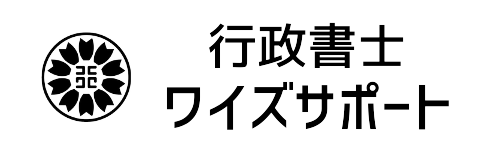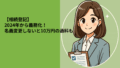相続で不動産を兄弟姉妹など複数人で分けるとき、「共有名義」にすることができます。
しかし、共有名義はトラブルの火種になりやすく、長期的に問題を抱える原因にもなります。
今回は、「共有名義の落とし穴」と題して、相続後に注意すべきポイントを解説します。
共有名義とは?

たけし
兄弟で1つの家を相続したら、とりあえず「共有」にすればいいのかな?

さとみさん
たしかにその場は丸く収まりますが、あとで売却や使用をめぐって揉めやすいんです。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で持つ権利形態です。
たとえば兄弟2人で1/2ずつ所有しているような状態が、共有名義にあたります。
共有名義の落とし穴
- 売る・貸すなどの処分に全員の同意が必要
- リフォーム・管理費の負担でもめる
- 相続が繰り返されると権利者が増えて複雑化
- 一部の人と連絡が取れなくなると手続き不能に

ふじはらさん
共有名義は「争族」の原因になりやすく、売却や賃貸がしたくても誰かが反対すると進みません。放置すると“塩漬け不動産”に。
解決策は?
- できるだけ単独名義にする
相続時に代償分割などを活用し、1人が取得して他の人に金銭で精算 - 持分の売却
不動産会社や他の共有者に持分を売る方法もあります(買い手は限定されます) - 共有者でルールを文書化
使用や費用負担のルールをあらかじめ取り決めておく
まとめ:共有名義は“仲が良いうち”に対策を
- 共有名義はトラブルのもとになりやすい
- 相続のたびに複雑化していく
- 単独名義化や明確なルール作りで将来の負担を減らそう
「とりあえず共有」はその場しのぎにしかなりません。時間が経つほど解決が難しくなるため、早めの対策が重要です。
共有名義で悩んでいる方は、私たち専門家へご相談ください。