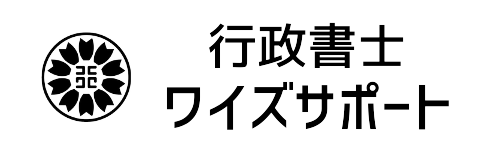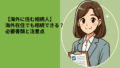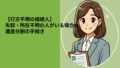相続人の中に障がいを持つ方がいる場合、手続きが通常よりも複雑になることがあります。
「知的障がいや精神障がいがある場合は?」「遺産分割協議はどうするの?」といった疑問を持つ方に向けて、今回は相続手続きの注意点や活用できる制度について解説します。
障がいがあっても相続人になれる?

うちの妹は障がいがあるんだけど、それでも相続人になれるの?

もちろんです。障がいがあるかどうかに関係なく、法律上の相続権は変わりません。
民法では、障がいの有無にかかわらず、相続人としての権利は守られています。相続分も、他の相続人と同様に認められます。
判断能力が不十分な場合の対応は?

でも、うまく話せなかったり、書類にサインできなかったりする場合はどうなるの?

そのような場合は「成年後見制度」を活用して、代わりに手続きを行ってもらうことができます。
判断能力が不十分な方がいる場合、そのままでは遺産分割協議が成立しない可能性があります。そうしたときは、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」などを選任することで、法的な代理人が代わりに手続きできます。
成年後見制度の種類と選び方

成年後見人って誰でもなれるの?お金もかかるのかな?

家庭裁判所が適任者を選びます。親族がなることもありますし、司法書士や行政書士などの専門職が選ばれることもありますよ。
成年後見制度には、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、本人の状態に応じて選ばれます。
後見人の報酬は本人の財産から支払われるのが一般的です。
遺言書で配慮することも可能

障がいのある子に多めに財産を残したい場合は、遺言書を活用するのが効果的です。
法定相続分では不安がある場合、遺言書を作成することで、障がいのある方に多めに財産を分けることができます。
遺言執行者を指定しておくことで、より確実に遺志を実現できます。
まとめ
- 障がいの有無にかかわらず相続権はある
- 判断能力が不十分な場合は成年後見制度を利用
- 後見人は家庭裁判所が選任する
- 遺言書で将来の生活支援を設計することも大切
相続人に障がいがある場合、配慮と準備がとても重要です。状況に応じて制度を活用し、ご家族みんなが安心できる相続を実現しましょう。
お困りの際は、私たち専門家へ相談を。