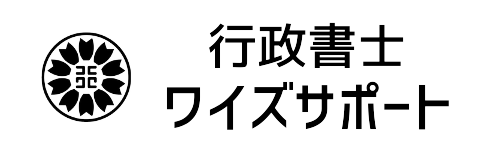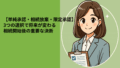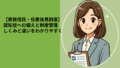「親が認知症になってしまったら、相続の準備はもう遅いの?」
そんな不安の声をよく耳にします。
実は、認知症になる前にできる対策も、なった後にできる手続きもあります。
今回は、認知症と相続の関係、そして適切な備えについてわかりやすく解説します。
認知症になると相続対策が難しくなる理由

認知症になったら、もう遺言書とか作れないの?

はい。本人の判断能力が失われると、遺言書や贈与契約は無効になることがあります。
遺言書や贈与契約などの法律行為は、本人に「意思能力」があることが前提です。
認知症が進行して判断力がなくなると、その人名義の財産を処分したり、名義変更をしたりすることが難しくなってしまいます。
対策1:元気なうちに「遺言書」を作っておく

親がまだ元気なうちに、何をしておけばいいの?

まずは「公正証書遺言」などを準備しておくのが安心です。
遺言書は本人が元気なうちに作成する必要があります。特におすすめなのが「公正証書遺言」です。
公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、後から無効になるリスクが低いのが特徴です。
対策2:家族信託や任意後見制度の活用

最近は「家族信託」や「任意後見制度」も注目されています。元気なうちに準備できるのがポイントです。
判断能力があるうちに財産管理を委ねる仕組みとして:
- 家族信託:財産を家族に託して、将来の管理や処分をあらかじめ決めておける
- 任意後見契約:判断能力が落ちたときに備えて、信頼できる人を後見人に指定
これらは、将来のトラブル防止やスムーズな財産管理に非常に有効です。
すでに認知症になった場合の対応

もう認知症が進んでしまった場合は、どうすればいいの?

その場合は「成年後見制度」を使って、家庭裁判所に申立てを行うことになります。
すでに意思能力がない場合は、成年後見制度を利用して家庭裁判所に後見人の選任を申請します。
ただし、成年後見人の行動には制限も多く、不動産の売却や贈与は家庭裁判所の許可が必要になります。
まとめ:早めの準備がすべてを左右する
- 認知症になると財産の手続きが難しくなる
- 元気なうちに「公正証書遺言」「家族信託」「任意後見契約」などを検討
- すでに認知症の場合は、成年後見制度で対応
相続対策は「元気なうち」だからこそできることがたくさんあります。
「まだ早いかな」と思っても、家族で話し合い、必要な備えを進めておくことが大切です。
不安なときは、私たち専門家へ相談を。