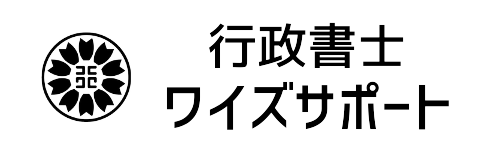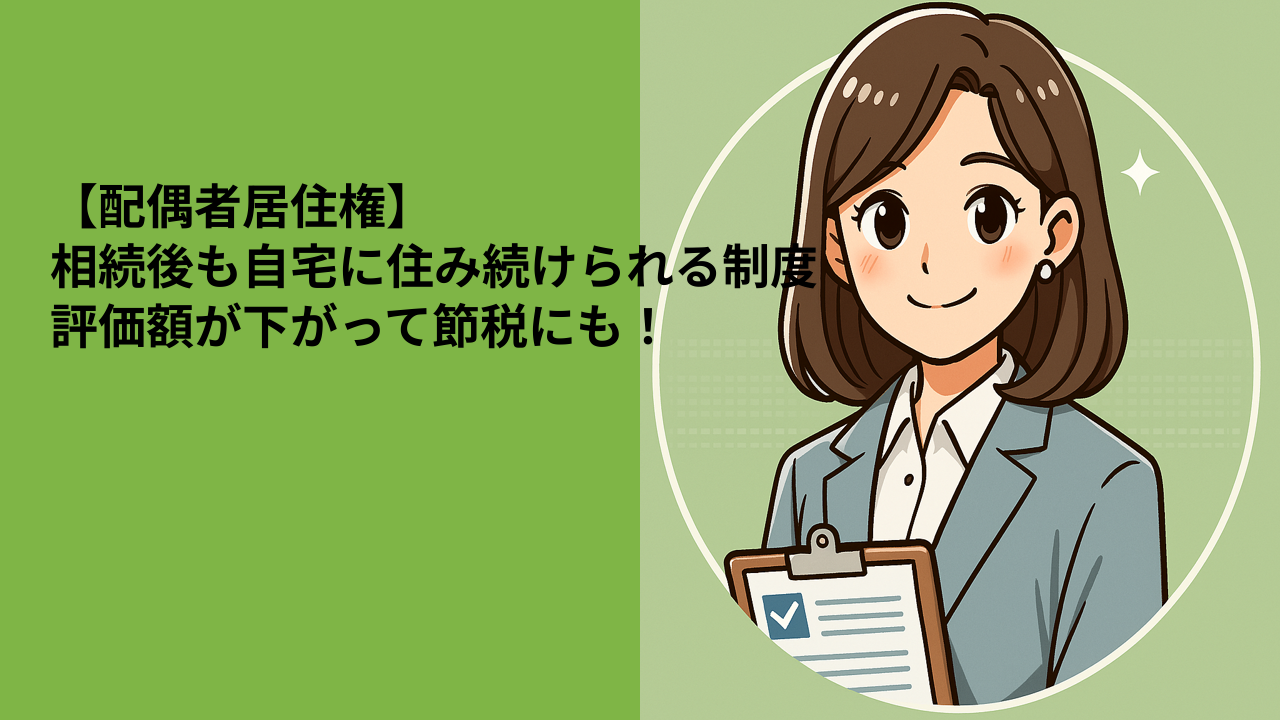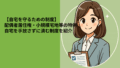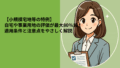相続が発生した際、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられるかは、とても重要な問題です。
その悩みを解消する制度が「配偶者居住権」。2020年の法改正で新設された、注目の制度です。
配偶者居住権とは?

たけし
家の名義が亡くなった人だったら、配偶者は出ていかないといけないの?

さとみさん
いえ、「配偶者居住権」を活用すれば、配偶者はそのまま自宅に住み続けることができるんです。しかも、その分の相続税評価額が抑えられるというメリットも。
どんな場合に使えるの?
- 亡くなった配偶者が自宅の所有者だった
- 残された配偶者が引き続き住み続けることを希望している
- 遺言や遺産分割協議によって配偶者居住権を設定する
法的には、被相続人の死亡時にその建物に住んでいたことが必要です。
どんなメリットがある?
- 配偶者が生涯、自宅に住み続けられる
- 建物全体を相続しなくてもよい(=他の相続人と分けやすい)
- 評価額が通常の所有権より低くなるため、相続税が節税できる
注意点・デメリットも

ふじはらさん
配偶者居住権は「住む権利」だけで「売る権利」はありません。将来的に売却や建て替えを検討している場合は別の対策が必要になることもあります。
- 居住権の登記が必要(手続きが煩雑)
- 居住権は譲渡や売却ができない
- 将来的に空き家になると管理負担が残る
相続税評価のイメージ
例:土地建物の評価が4,000万円の場合――
- 通常の相続:4,000万円全額が課税対象
- 配偶者居住権を使う:評価額が2,000万円以下に圧縮
まとめ:住まいを守る、思いやりの制度
- 配偶者居住権で、自宅を失わずに安心して暮らせる
- 相続税の節税効果もある
- 登記や手続きのサポートは専門家と一緒に
配偶者の住まいを守る「配偶者居住権」は、相続対策の強い味方です。
制度の活用や手続きに不安がある方は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。