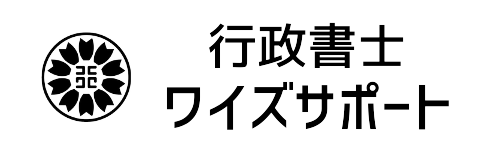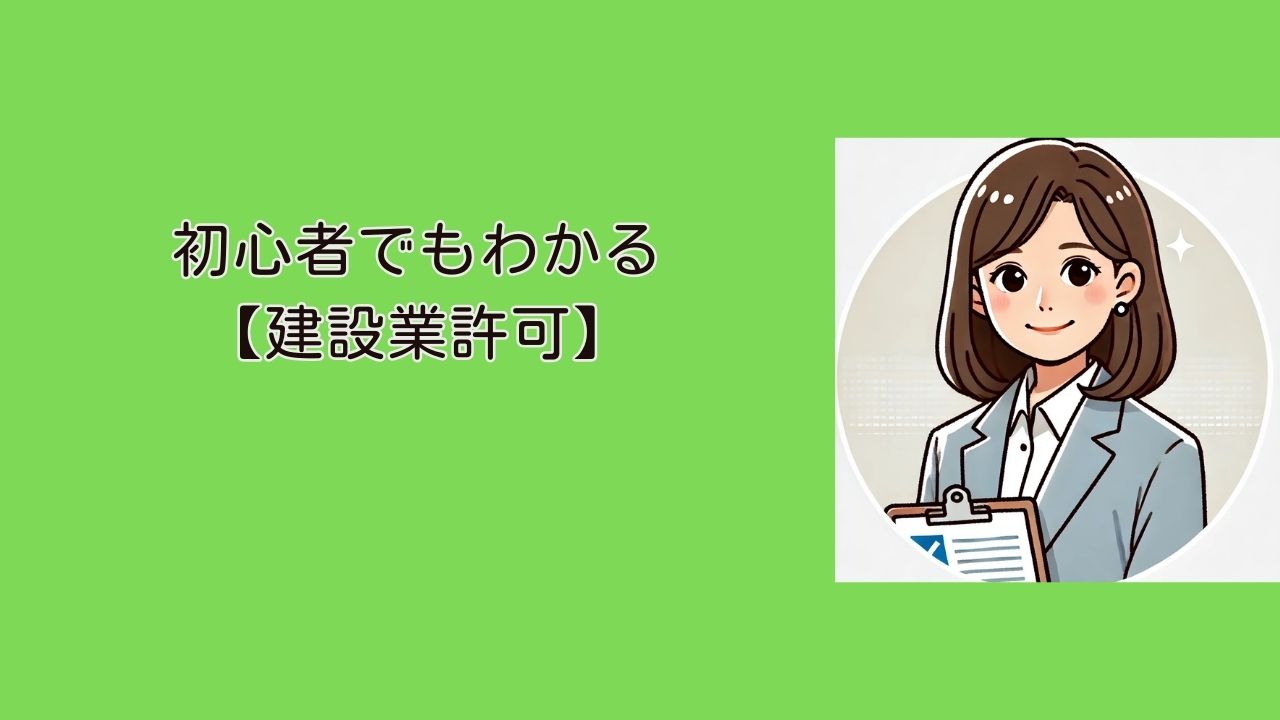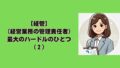はじめに
建設業界で仕事の幅を広げていくためには、「建設業許可」の取得がひとつの大きなステップになります。とくに大阪府のように事業者の多い地域では、取引先からの信頼を得るためにも「許可業者」であることは大きなアドバンテージです。
でも実際、「許可が必要なのはどんなとき?」「どんな書類がいるの?」と疑問が尽きない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、大阪府で建設業許可を取得するための基礎知識から、申請の流れ、注意点までを初心者向けにわかりやすくまとめました。
第1章|建設業許可が必要なケースとは?
建設業を営む上で、すべての工事に許可が必要というわけではありません。実は、一定の規模を超える工事に対してのみ許可が必要とされています。
🔸 許可が必要な工事の基準
建設業法では、以下のように定められています:
「工事1件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)」
→ この場合、建設業許可が必要
つまり、たとえば内装工事で400万円の案件であれば許可がなくても施工可能ですが、600万円の外構工事を請け負う場合は許可が必要です。
🔸 軽微な工事の具体例
- 住宅のリフォーム(壁紙の張り替えなど)→ 許可不要
- 大型マンションの外壁改修工事(800万円)→ 許可必要
- 塗装工事で350万円 → 許可不要
- 設備工事(空調や配管)で600万円 → 許可必要
この「500万円以上ルール」は税抜きではなく税込み金額でカウントする点も要注意です。
🔸 元請けでも下請けでも対象になる
「自分は元請けじゃないから大丈夫」と思っている方も注意が必要です。許可の有無は、元請・下請どちらでも関係なく適用されます。
さらに、500万円以下の工事しかしていない場合でも、将来的な事業展開や取引先の信頼確保のために、早めに許可を取得しておくケースも増えています。
ありがとうございます!それでは続きを執筆します。「第2章|建設業許可の種類と選び方」です。
第2章|建設業許可の種類と選び方
建設業許可にはいくつかの種類があり、自分の業務内容や規模に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。ここを間違えると申請が通らなかったり、事業拡大の足かせになったりするため注意が必要です。
🔸 一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に大別されます。
| 区分 | 概要 | どんな業者に向いているか |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 下請けに出す金額が1件につき4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) | 中小規模の施工業者、元請も可 |
| 特定建設業 | 下請けに4,000万円以上の発注をする元請業者 | 大規模工事を受注する元請業者向け |
**多くの中小事業者が該当するのは「一般建設業」**です。特定建設業は、かなりの規模感と財務的な裏付けが必要になるため、初めての許可申請で選ばれることはあまり多くありません。
🔸 建設業の業種(全29業種)
建設業許可は1つの業種につき1許可です。業種は全部で29種類あり、代表的なものは以下のとおりです:
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- 管工事業(配管など)
- 電気工事業
- 塗装工事業
- 内装仕上工事業 など
たとえば「内装仕上工事業」と「電気工事業」の2つを請け負いたい場合は、それぞれに許可が必要です(申請は同時に可能)。
🔸 大阪府で多い申請業種ランキング(※参考)
大阪府でよく申請されている業種には次のような傾向があります:
- 内装仕上工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 建築工事業
- 塗装工事業
都市部ならではのリフォーム・設備工事需要が多いため、こうした業種での申請が目立ちます。
🔸 自分に合った選び方のポイント
- 現在の施工内容を明確にする
- 今後対応したい業務も含めて検討する
- 発注者(元請・下請)との関係性を考慮する
- 複数業種を取得するか、段階的に取得するか検討
了解しました!それでは「第3章」から「まとめ」まで、一気に仕上げますね。
第3章|大阪府での申請方法と流れ
大阪府で建設業許可を取得するには、府庁の建築振興課を通じて申請する必要があります。ここでは、申請の全体像をステップごとに解説します。
🔸 申請のステップ(全体の流れ)
- 要件確認・書類の収集
- 経営業務の管理責任者や専任技術者がいるかを確認
- 登記簿謄本、納税証明書などを取得
- 申請書の作成
- 様式に沿って必要項目を記入
- 業種ごとに追加書類が必要なことも
- 大阪府に提出(郵送 or 持参)
- 原則、法人は本店所在地を管轄する府庁(咲洲庁舎)
- 審査期間(約1ヶ月~2ヶ月)
- 不備がなければそのまま審査へ進む
- 許可通知が届く
- 許可が下りると「建設業許可通知書」が届く
🔸 事前相談は強くおすすめ!
書類に不備があると、申請が長引いたり、再提出になることも。大阪府では事前相談窓口を設けており、活用することでスムーズな申請が期待できます。
🔸 オンライン申請はできる?
2025年現在、大阪府ではオンライン申請には未対応です(今後導入の可能性あり)。申請は紙ベースでの提出が必要です。
第4章|申請に必要な書類一覧
建設業許可の申請には、事業者の形態(法人か個人)によって異なる書類が必要です。以下は代表的なものです。詳細は大阪府ホームページの「建設業許可申請の手引き」をご参照ください。
🔸 法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 納税証明書(法人税)
- 決算書(直近2期分)
- 経営業務の管理責任者に関する証明書
- 専任技術者の資格証明書(免許証など)
- 営業所の写真・使用権限を示す資料(賃貸契約書など) など
🔸 個人の場合
- 住民票
- 納税証明書(所得税)
- 所得税の確定申告書(直近2年分)
- その他、法人と同様に必要な資格証明など
🔸 よくあるミス
- 証明書が発行から3ヶ月以上経過している
- 提出書類の不一致や抜け
- 賃貸契約書の名義が一致しない
→ 書類の整合性は、非常に厳しくチェックされるので注意が必要です。
第5章|費用・期間の目安
🔸 大阪府への申請手数料(法定費用)
- 知事許可(大阪府内のみ)… 90,000円
- 大臣許可(複数都道府県で営業所)… 150,000円
🔸 行政書士に依頼する場合の費用相場
- 一般的に150,000円~300,000円程度が多いです(弊所調べ)
- 弊所では、たとえば大阪府知事許可(一般・法人・新規)で110,000円です。
- 業種の数や法人・個人の違いで変動あり
🔸 許可までの期間
- 書類が整っていれば約1~2ヶ月
- 不備があるとさらに時間がかかることも
第6章|許可後に必要な手続きと注意点
建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。維持するためには定期的な手続きが求められます。
🔸 年次の「決算変更届」
- 毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要
- 提出を怠ると更新ができなくなることも
🔸 許可の更新
- 許可は5年ごとの更新制
- 更新には改めて手続きと費用が必要
🔸 現場での標識表示義務
- 許可番号や業種、名称を現場に表示する義務があります
第7章|行政書士がサポートできること
建設業許可の申請は、書類の量も多く、要件も複雑です。そういった負担を軽減できるのが行政書士のサポートです。
🔸 行政書士ができること
- 書類の収集代行
- 要件の確認・整理
- 認定証や証明書の取得サポート
- 許可後の継続サポート(決算変更届・更新など)
🔸 実際のサポート事例(例)
「自社だけでは書類が集められず、何度も府庁に行く羽目になっていたが、行政書士に依頼してから1回で完了できた」
まとめ
大阪府で建設業許可を取得するには、専門的な知識としっかりした準備が必要です。しかし一度取得すれば、受注できる案件の幅も信頼も一気に広がります。
- どんな工事で許可が必要なのか?
- どの区分・業種で申請すべきか?
- どのくらいの費用・期間がかかるのか?
これらが明確になった今、次にやるべきは「行動」です。迷ったら、まずは行政書士に相談して、最短ルートでの許可取得を目指しましょう!