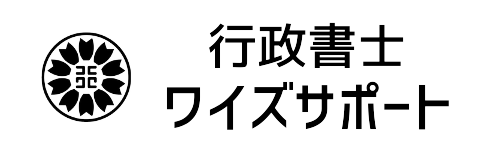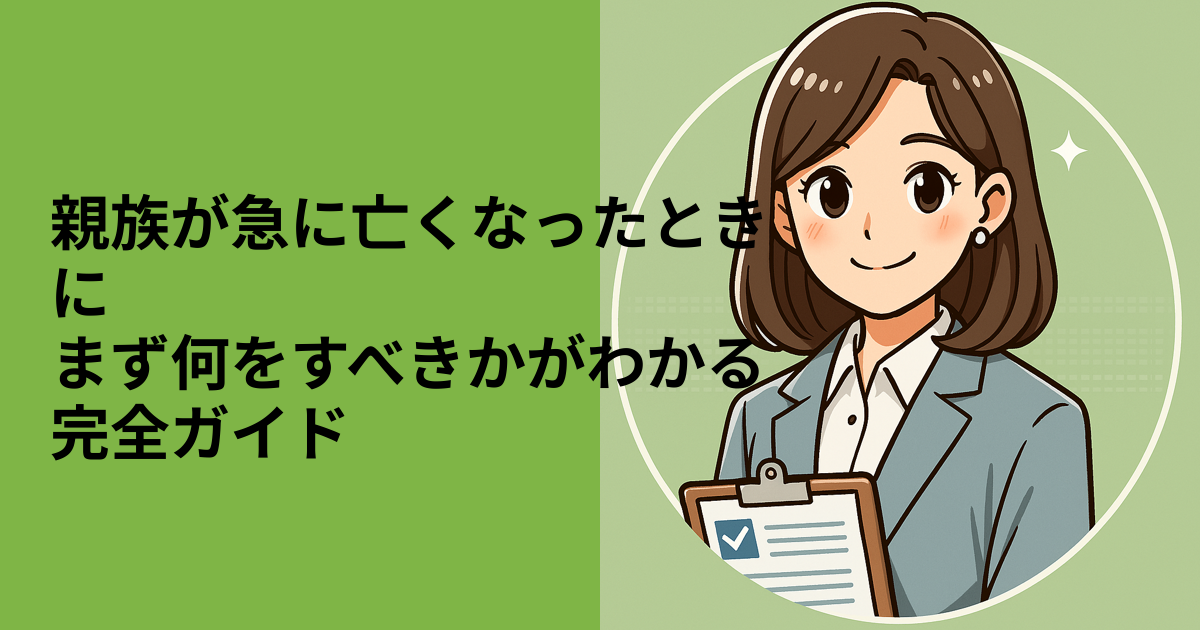
動揺して当然。でも「やるべきこと」は待ってくれない

昨日まで元気だった親が、急に倒れて亡くなってしまって…頭が真っ白で、何から手をつけたらいいのか本当に分からなかったよ。

突然のことで気持ちの整理もつきませんよね。でも、亡くなった直後にやらなければならないことがいくつかあります。順番に確認していきましょう。
【STEP1】死亡診断書の取得と死亡届の提出
亡くなられた直後にまず必要なのが「死亡診断書」の取得です。病院で亡くなった場合、医師が発行してくれます。自宅で亡くなった場合は警察の立ち会いのもと検案書が必要になるケースもあります。
この死亡診断書をもとに、7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出します。提出するのは、通常は親族または同居人ですが、葬儀社に委任することも可能です。
【STEP2】火葬許可証の取得と安置・搬送
死亡届を提出すると、同時に「火葬許可証」が発行されます。この許可証がないと火葬はできません。取得後は、遺体を安置する場所へ搬送します。
搬送先としては、自宅、葬儀場の安置室、霊安室などがあります。どこに安置するかによって、以降の準備の進め方も変わってきます。
【STEP3】親族・関係者への連絡と葬儀社の手配
葬儀社の手配と同時に、親族・友人・職場など関係者への連絡も進めます。最近はLINEグループなどで情報共有するご家族も増えています。
また、菩提寺がある場合は、宗派の確認や僧侶の手配もこのタイミングで行います。
【STEP4】葬儀・通夜の準備
葬儀の形式は、一般葬、家族葬、直葬など様々です。それぞれにメリット・デメリットがあります。
- 一般葬:多くの方が参列しやすいが、費用と準備が大きい
- 家族葬:限られた身内で落ち着いてお別れできる
- 直葬:通夜・葬儀を省略して火葬だけ行う、経済的だが後悔の声も

うちは高齢の親族ばかりで、遠方の人も多いから、家族葬にしようか迷ってるんだよね。

事前に親族の意見も聞いておくと良いですよ。後から「会いたかった」と思う方がいると悔いが残ることもあります。
【STEP5】死亡後の行政手続き
葬儀が終わったあとにも、たくさんの行政手続きが待っています。以下のような項目は忘れずにチェックしておきましょう。
| 手続き | 内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 健康保険の資格喪失届 | 国保または社保を脱退 | 14日以内 |
| 年金の停止手続き | 受給停止と未支給年金の請求 | なるべく早く |
| 住民票の抹消 | 通常は死亡届で自動処理 | ー |
| 公共料金などの名義変更 | 電気・水道・ガスなど | 随時 |
| 銀行口座の凍結・相続対応 | 預金引き出し不可、遺産分割協議へ | ー |
チェックリスト:やるべきことまとめ
- ☑ 死亡診断書を取得する
- ☑ 死亡届を提出する
- ☑ 火葬許可証を受け取る
- ☑ 葬儀社を手配する
- ☑ 遺体を搬送・安置する
- ☑ 親族・関係者に訃報を伝える
- ☑ 僧侶や宗教者を手配する
- ☑ 通夜・葬儀の形式を決める
- ☑ 年金・健康保険の手続きをする
- ☑ 相続関係の整理・相談を始める
まとめ:大切なのは「誰かに頼る」こと

一人で抱え込まないで。行政書士や葬儀社、役所の窓口も含めて、頼れる人に頼ることが、最善の選択になることもあります。
この記事が、突然の悲しみに直面した方にとって、少しでも行動の道しるべになりますように。

お問合わせ
ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください(初回60分無料)