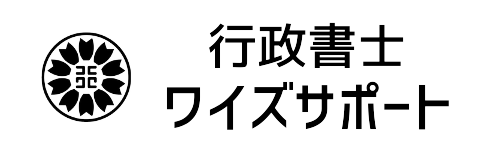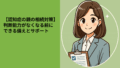「親がもし認知症になったら、通帳や不動産の管理はどうなるの?」
そんな不安を抱えるご家庭は少なくありません。
近年注目されているのが、「家族信託」と「任意後見制度」です。
どちらも将来のための備えとして有効ですが、仕組みや使い方には違いがあります。
家族信託とは? 自由度の高い財産管理の手段

たけし
家族信託って、どんな制度? だれが何を信じるの?

さとみさん
「親=委託者」が「子ども=受託者」に財産の管理を託す制度です。契約内容は自由に設計できますよ。
家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す仕組みです。
特徴:
- 不動産や預金の管理・処分が柔軟にできる
- 本人が元気なうちに契約する
- 公的な監督は原則なし(自由度が高い)
- 家庭裁判所の関与が不要
例えば、認知症に備えて親名義の不動産を子が管理し、将来は孫へ引き継ぐ設計も可能です。
任意後見制度とは? 判断力が落ちた後に効力を発揮

たけし
任意後見って、後見人を自分で選べる制度なの?

さとみさん
はい。将来認知症などで判断力が落ちた時に備え、後見人をあらかじめ契約で決めておけます。
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、後見人との契約を結んでおく制度です。
特徴:
- 契約時点では効力なし(将来発動)
- 本人に判断能力がなくなったとき、家庭裁判所で発動
- 家庭裁判所が監督するため安心感がある
- 日常的な財産管理や契約行為の代理が可能
家族信託と任意後見の違いは?
以下のように、制度の目的や使えるタイミングに違いがあります。
| 項目 | 家族信託 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 契約直後から | 本人の判断力低下後 |
| 監督機関 | 原則なし | 家庭裁判所が監督 |
| 財産処分の自由度 | 高い | 制限がある(法律に従う) |
| 相続対策との相性 | 非常に良い | 補完的な役割 |
まとめ:目的に応じた制度の活用を
- 家族信託は、生前の財産管理や相続対策に有効
- 任意後見は、本人が判断できなくなった後の支援に安心
- どちらも、元気なうちに契約する必要がある
- 制度の選択には専門家のアドバイスが不可欠
家族のこれからに備えて、今からできることを始めてみませんか?
どちらの制度がご家庭に合っているか知りたい方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。