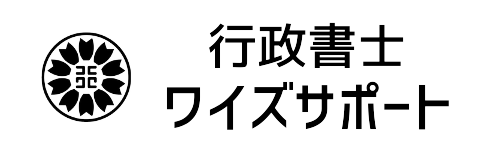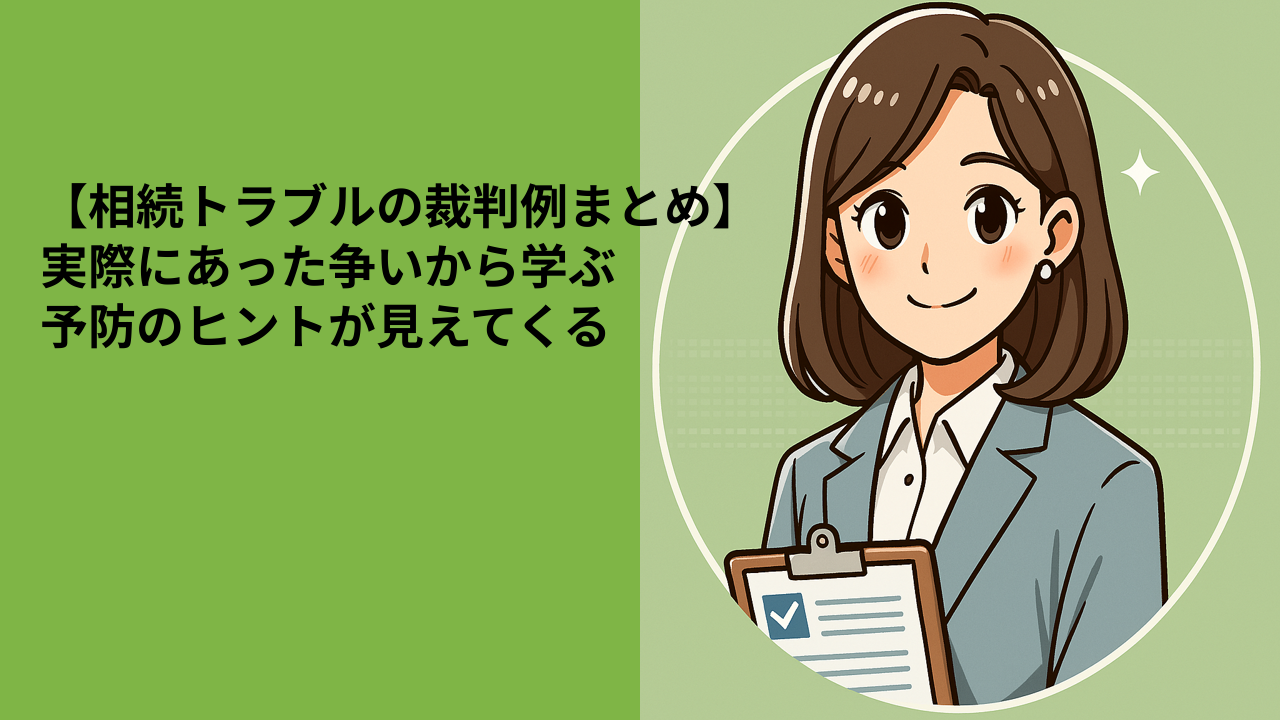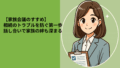「まさかうちの家族が…」
そう思っていたのに、相続をきっかけに争いが起きてしまったという声は後を絶ちません。
今回は、実際の裁判例をもとに、どのような経緯でトラブルに発展したのか、そしてどうすれば防げたのかを見ていきましょう。
裁判例1:長男がすべての財産を相続しようとしてもめた

うちは昔から「長男が家を継ぐ」って決まってたけど、それでいいんじゃないの?

でも、法律上は他の兄弟姉妹にも「法定相続分」があります。勝手に独占するとトラブルになりますよ。
事案概要:父の死後、長男が実家と預金をすべて相続したいと主張。他の兄弟は「不公平だ」と反発し裁判に。
裁判所の判断:遺言書がなく、法定相続分に従って分けるべきと判断。長男の単独取得は認められませんでした。
ポイント:「慣習」や「話し合いで済むだろう」という油断が争いを招くことも。遺言書があれば結果は変わっていたかもしれません。
裁判例2:生前贈与が不公平とされたケース

兄だけ親からマンションを買ってもらってたけど、それって問題になるの?

はい。「特別受益」として相続時に調整の対象になります。
事案概要:生前に長男が親から住宅購入資金1,500万円を受け取っていた。他の兄弟はそれを知らず、相続時に発覚して大揉め。
裁判所の判断:長男の受け取った金額は「特別受益」とされ、相続分から差し引かれた。
ポイント:生前贈与がある場合はきちんと記録・共有をしておくべきです。そうでないと、後に不信感を生む原因になります。
裁判例3:介護してきた子どもに対する寄与分請求

親の介護を献身的に行っていた子どもが「寄与分」を請求することがありますが、必ず認められるとは限りません。
事案概要:長女が10年間親の介護をし、相続時に他の兄弟と同額では納得できないとして「寄与分」を主張。
裁判所の判断:介護内容・労力・費用負担を総合的に判断し、一部寄与分を認定。ただし全額分の上乗せは認められなかった。
ポイント:寄与分は裁判所の判断が難しく、明確な証拠(介護日記・費用記録など)が必要です。
まとめ:裁判になる前にできることがある
- 「慣習」や「感覚」だけで分けるとトラブルに
- 遺言書や生前贈与の記録は明確に残す
- 介護など家族内の貢献は、見える形に
- 何より「家族で話しておく」ことがトラブル防止に
裁判までいくと、時間もお金もかかり、家族関係にも深い傷が残ります。
だからこそ、予防のための備えが大切です。
「自分の家庭は大丈夫」と思わず、まずは一度、私たち専門家へ相談を。