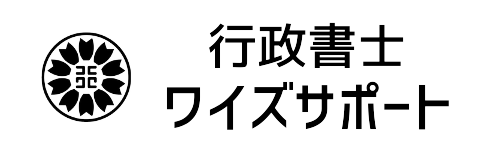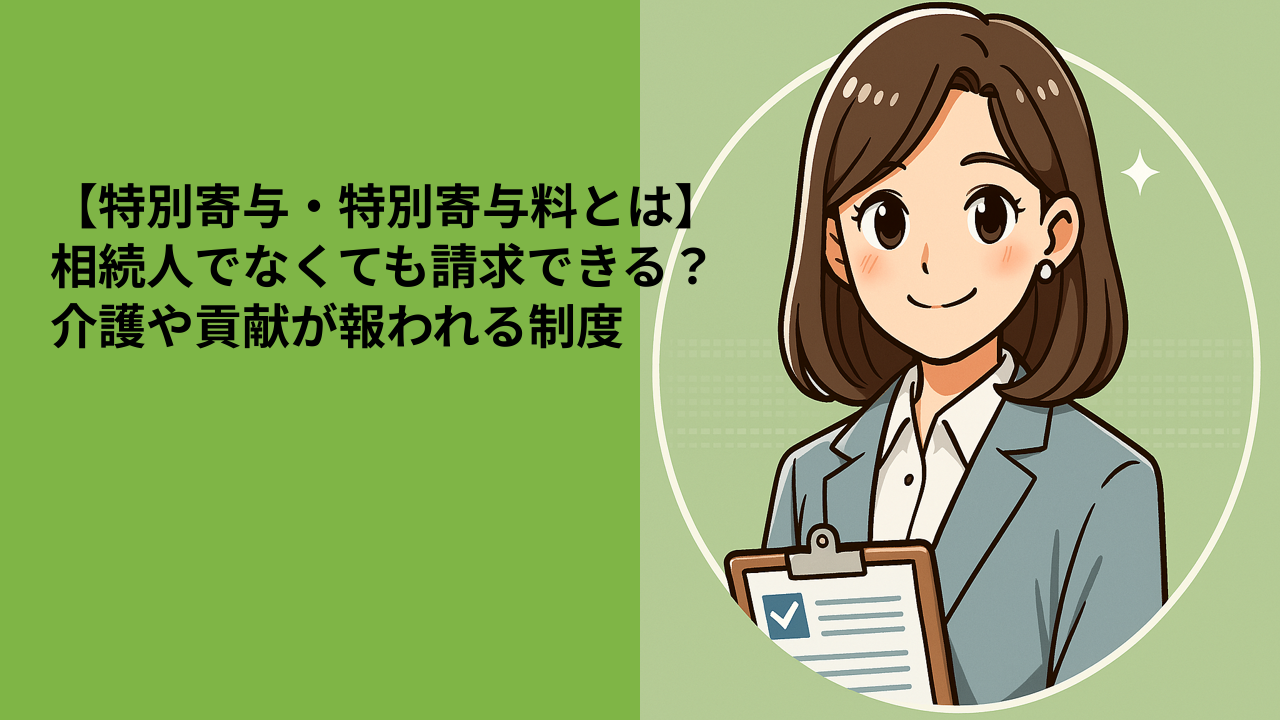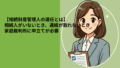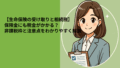亡くなった方に対して、長年介護や看護をしてきた親族がいる。
でもその人が相続人ではない場合、相続分がゼロというのは、不公平に感じることもあるでしょう。
そんなときに使える制度が、特別寄与料の請求です。
この記事では、2019年の法改正で新たに認められた「特別寄与」とは何かをやさしく解説します。
特別寄与とは?

たけし
相続人じゃなくても、おじいちゃんの介護をしたら何かもらえるの?

さとみさん
はい、2019年の民法改正で、相続人でなくても一定の貢献があれば「特別寄与料」を請求できるようになりました。
どんな人が請求できる?
- 被相続人(亡くなった方)の親族(例:長男の妻、兄弟の配偶者など)
- 生前の療養看護や介護など、無償で相続財産の維持・増加に貢献した人
請求方法と注意点
- 相続人に対して請求(家庭裁判所に申し立ても可能)
- 期限は相続開始と相続人を知ったときから6か月以内
- 金額は話し合いで決まらなければ裁判で判断

ふじはらさん
特別寄与料はあくまで「貢献に対する対価」です。日常的な手伝いや感情的な付き添いでは認められにくいので、証拠も大切になります。
認められる可能性のある例
- 長期間の自宅介護
- 通院・入退院の付き添い
- 生活費や医療費の一部を負担していた
- 農業や商売を手伝い、収益に貢献した
注意したいポイント
- 請求は相続人との交渉になるため、感情的な対立も起こりやすい
- 証拠の保存(メモ・日誌・領収書など)が重要
- 裁判になると時間も費用もかかる可能性あり
まとめ:介護の貢献は「特別寄与」で報われる
- 相続人でなくても、無償の貢献があれば請求可能
- 話し合いや証拠の整理が大切
- 感謝と公平の気持ちで、丁寧な対応を
長年の介護や支えが報われる制度、それが「特別寄与制度」です。
手続きに迷ったら、ぜひ私たち専門家へご相談ください。